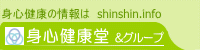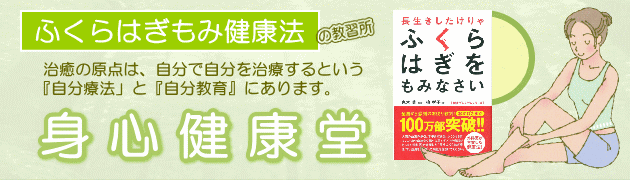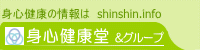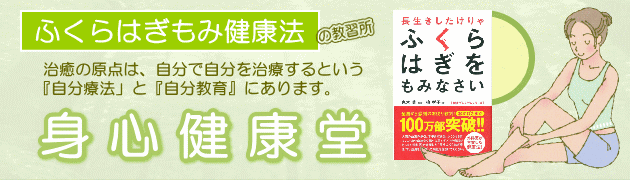|
����23�N6��18���i�y�j�ߌ�13�����`15�����܂ŁA�����s�����旧���������w�Z����A���t�E�ی�ҁE�����̊�]�҂�ΏۂƂ����u�ӂ���͂��}�b�T�[�W�u�K��v�̍u�K���˗����܂����B
�܂��A2��ڂ̍u�K��˗���25�N2��14���Ɏ܂����B
��1��̍u�K��ɓ��s��������D���u�K��̗l�q�����Љ�܂��B
����70���قǂł��傤���A�搶�E�ی�ҁE�����@�ی�҂͂���������A�����Ď����͒j�̎q�̎Q��������܂����B
���z�́E�E�E�y���������I�ꌾ�ł܂Ƃ߂����ł���
�Z���搶�͂��ߐ搶���A���������ĉ�������PTA�����̕ی�҂̕��X�̔M�ӂ������Ă����Q�����ꂽ���̈ӗ~���N���A�g�S���N���X�^�b�t���ӂ���͂��}�b�T�[�W�ɂ��Č��₷�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���������w�Z�Ɛg�S���N���Ƃ̂����́A�Z���搶�������g�̌��N�Ǘ��̈�Ƃ��āA�����ōs���Ă���u�ӂ���͂��}�b�T�[�W���K�u���v�ɎQ�����ꂽ���Ƃ���ł����B
��̉����l�X�ȕa�C�������N�������Ƃ́A���łɎ��m�̎��Ǝv���܂��B��l�����łȂ��A���q����܂ł����悪�₽���ӂ���͂����d���B�ӂ���͂��}�b�T�[�W�͓�������s�������ł��A����i�K�̏��w���ɂ͂܂��ɂ����Ă����I
�w�Z����ł͂�Ƃ苳��̌��ʂ�������u�w�͌���v������Ă��܂����A�w�͌���̂��߂ɉ���������̂ł͂Ȃ��A�Z���搶�́u�S�Ƒ̂���Ă�ƌ��ʂƂ��Ċw�͌���Ɍq����v�Ƃ̂��l���B
���N���ōs�����K�u���͗��_��������Ƃ��b���܂��̂ŁA�������́u���q�����ӂ���͂��}�b�T�[�W���ǂ���ł���v�Ƃ�����ƌ����������Z���搶�̏�X�l���Ă��邱�Ƃƃs�b�^���}�b�`���O���APTA�ɓ����|������̍u�K��̉^�тƂȂ�܂����B
����̏�ł��l�X�ȕ�����邩�Ǝv���܂����A�����Ɂu����͂����I�v�Ɗ��������̂͏����ɐl�̐S�ɐZ������̂��Ȃ��ƍZ���搶�̂��b���f���Ȃ��犴���A������ی�҂̔M�ӂ��������̂��I�I�Ɣ[�����܂����B
���Ă��āA�O�u���������Ȃ�܂������A����͗��_�͂Ȃ��I�i���_�͑�ł����̌����鎞�Ԃ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂Łj
�u�K��̒��ŁA�l�X�ȂԂ₫������܂���
�ӂ���͂����Ăǂ��H���ނ��Ăǂ�����āH�H�@
����ŗǂ���ł��I
�^�₪�N������Ԃ₢�āA�݂�Ȃŋ^������L����ƁA�ĊO�����̂��Ƃɓ��Ă͂܂��Ă����肵�܂��Ɛg�S���N���̉@�����搶�͏�X�����Ă��܂��B
��ۓI���������Ƃ́A���q������ӂ���͂����₦�Ă������ƁB������O�Ȃ��Ƃł����A���q����͗₽�����Ƃ�������O�Ǝv���A�₦�Ă���Ƃ��������o������܂���B���F�B�̂ӂ���͂��Ɣ�ׂĎ����̂ӂ���͂��͗₽�����I�Ǝ������A�܂��͎����̑̂ɋ����������Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ꂩ��ӂ���͂��}�b�T�[�W���ł���̂ō��₽���Ă����ꂩ����P�ł��邱�Ƃ�`���܂����B
���q����͂��ꂳ��E��������̂��߂ɁA�ی�҂̕��͂��q����̂��߂ɁA�a�C���������Ƃ��Ȃ���ӂ���͂��}�b�T�[�W�����Ă�����i�́A��������S���g�����Ȃ�܂����B���ꂳ��̃}�b�T�[�W�ŃX���X���ƐQ�Ă������q��������܂����B
�����̑̂ƌ����������Ԃ����Ă����Ƃ�e�q�̃R�~���j�P�[�V�����ɂ��ӂ���͂��}�b�T�[�W�̓}�b�T�[�W�ȏ�̌��ʂ��ł�I�Ɖ������Ƃɂ��܂����BD�ł���
�u���������w�Z�̍u�K��v
����2011�N6��18���i�y�jPM1:30�`3:30�܂œ����s�����旧���������w�Z�ɉ����āA���k�E�ی�ҁE���t�����i�Q����]�ҁj�u�ӂ���͂��}�b�T�[�W�v�̍u�K����J�Â����B�g�S���N���̏o�Ȏ҂́A��\�̋S�ؖL�A�@���̖��F�q�A�A�V�X�^���g�Ƃ��Đ��V�A���Ōv4���B
�܂��A�Z���̊O�쐟�q�搶����w���������w�Z�̐��k�����Ɍ��N�ŋ����g�S��b���A���ː_�o�̏r�q�Ȏq�ǂ��Ƃ��Đ������ė~�����B���̂��߂ɂ́A���ł��A�ǂ��ł��A�N�ł��ȒP�ɂł���u�ӂ���͂��}�b�T�[�W���N�@�v����ԗǂ��Ǝv���č���A�u�K����J�Â��邱�ƂɂȂ����B�x��|�̈��A���������B
�����ċS�ؖL��\�̂������̏I���A�݂�Ȃْ̋��������Ӗ��������āA70���O��̎Q���҂Ƌ��Ɂu���̑̑��v�����{�B
�q�ǂ�����l���S�u���Ȃ���������āA�吺�肠���āA�N�͂��邱�ƂȂ����A��C�ɋْ��������āA���̃��[�h���a�₩�Ɉ�ς����B
���F�q�@�����A�ɂ��₩�ȃX�}�C���ŁA�w�ӂ���͂��}�b�T�[�W�x�̎��K�w���Ɉڂ����B
�w�Z�̑̈�قɃ}�b�g���~�ɂȂ��Ċۂ��~���l�߁A�^���ɖ��@�����ʒu���āA�ŏ��̓E�H�[�~���O�A�b�v�B
�����Ĉ�l�ł��u�ӂ���͂��}�b�T�[�W�v
�ی�҂���͎�����q�ǂ��̌��N���k���������B���͋C�͐���オ��������A�Q���ґS������̂ƂȂ��ď��������ϊy�������ł������B
���@���̎��K�w�����z�Ƃ��ăn�L�n�L�B�݂�ȂƈӋC����������Ԃ������o���āA�������ɏI�������B
�O��Z���搶�͂��ߎQ���������t�̊F����ɂ����ł�������l�q�ł������B
���E���w�Z��ΏۂƂ������̎�́u�ӂ���͂��}�b�T�[�W�v�̍u�K��́A���k�E�ی�ҁE���t�����̌��N���K�ɂƂǂ܂炸�A���݊Ԃ̃X�L���V�b�v�A�R�~���j�P�[�V�������������̃j�[�Y�Ƀs�b�^�����v�������̂Ǝv����B
|